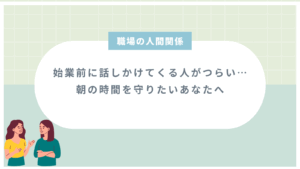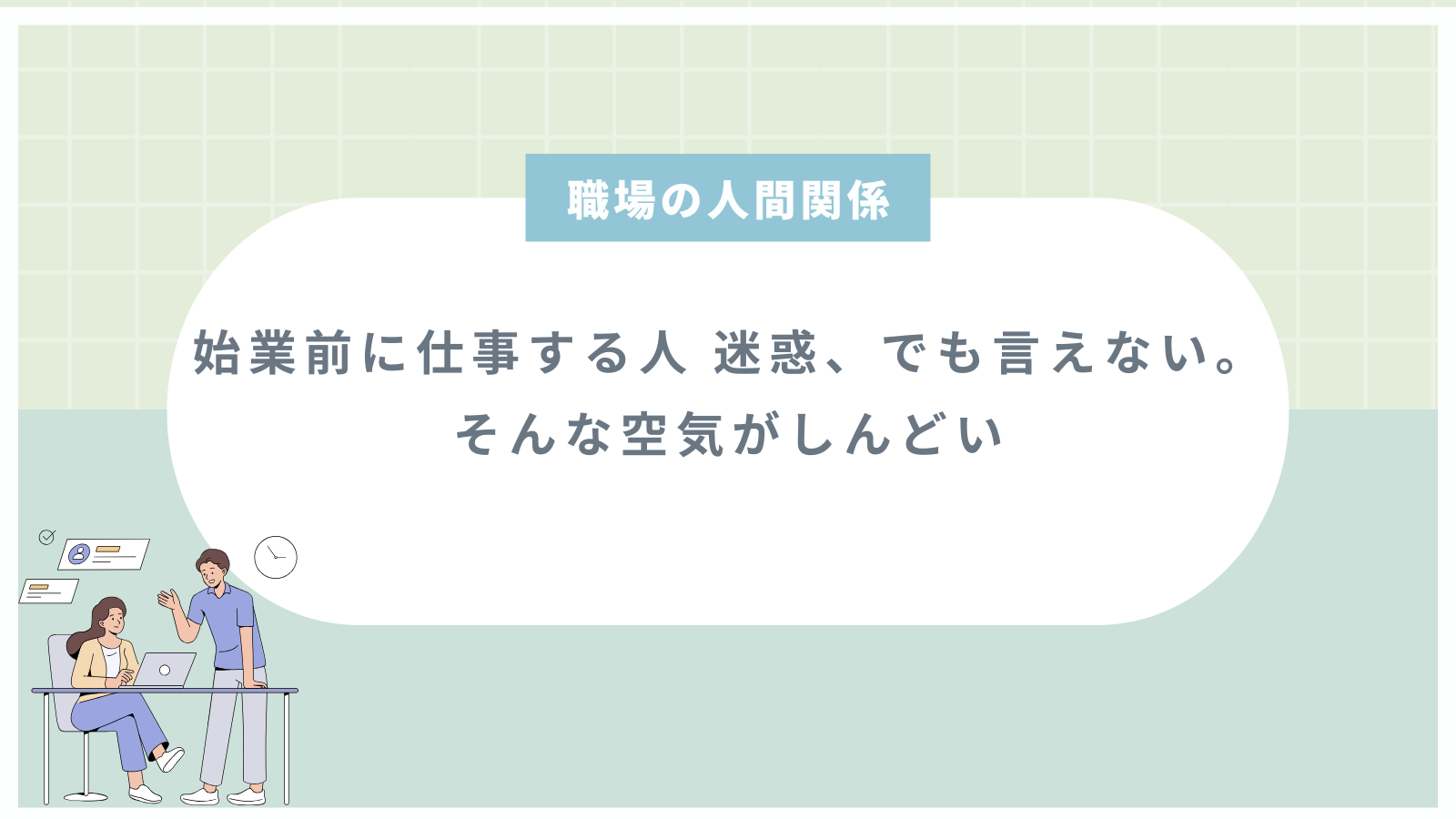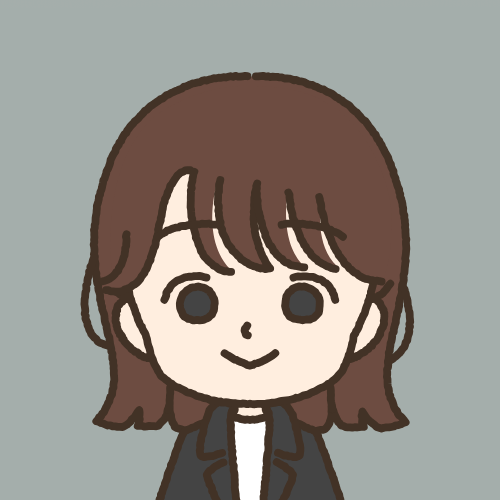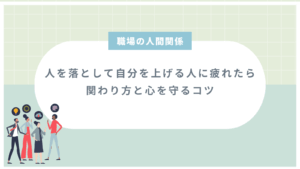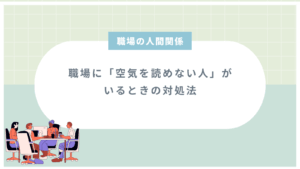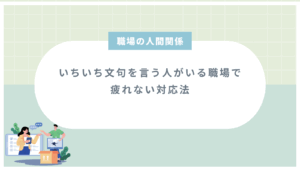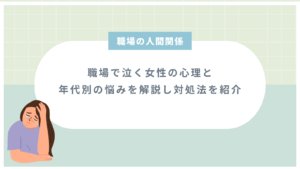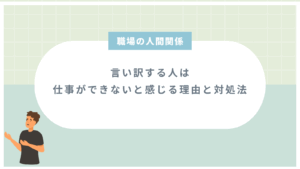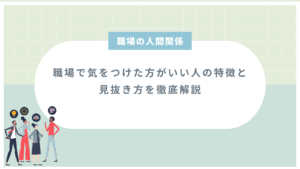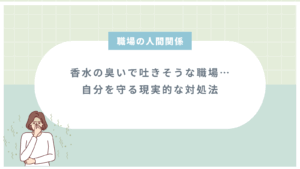朝、いつもどおりに出勤したら、すでに何人かが仕事を始めていた。そんな場面に出くわして、なんとなくモヤモヤした経験はありませんか?始業前に仕事する人がいると、真面目で頑張っているように見える一方で、「迷惑だな…」と感じてしまうこともありますよね。
この記事ではそう思ってしまう理由や、そう感じる側・感じさせる側それぞれの心理について深掘りしていきます。
なぜ周囲がプレッシャーを受けるのか、どんなトラブルの火種になるのか──あの独特な“職場の空気”を少しでも軽くできるよう、ヒントをお届けします。
- なんで“早く来て働く人”にモヤモヤしてしまうのかがわかる
- 「自分だけ焦ってるのかも…」という空気の正体に気づける
- その行動がルール違反になってしまう理由が見えてくる
- 自分のペースを守りながら、職場とちょうどよく付き合うヒントが見つかる
始業前に仕事する人、やっぱり迷惑?そう感じる理由とは

どうして早く来すぎる人が迷惑に思われるの?
職場に早く来て仕事を始める人は、見た目には真面目で一生懸命に見えるかもしれません。ただ、その行動が周囲に影響を与えてしまい、「ちょっと迷惑かも…」と感じさせてしまうことがあります。
なぜなら、周囲が「自分も早く来ないといけないのかな」と無言の圧を感じてしまうからです。本来、仕事は始業時間から始めればいいものの、誰かがその前から働き出していると、知らず知らずのうちに「早く来るのが当たり前」という空気が広がってしまうことがあります。
たとえば、毎朝30分前に出勤して資料作成を始めている人がいると、時間どおりに来た人が「自分だけ出遅れてるかも」と感じてしまう場合もあります。決して遅れているわけではないのに、心のどこかで焦ってしまうこともあるでしょう。
こうした感情が続くと、表立って文句を言われるわけではないものの、職場の空気が少しずつ重くなっていくこともあります。特にチームで動く職場では、誰かの“先回り行動”が周囲との温度差を生みやすくなるのです。
ここからは、こうした行動が実はルール違反につながる可能性について見ていきます。
始業前に働くことがルール違反になることも
早めに出勤して業務を始めることが、場合によっては就業ルールの違反になることがあります。なぜかというと、多くの職場では「勤務時間は始業から終業まで」と定められており、それ以外の時間に仕事をするには管理や許可が必要とされているからです。
たとえば、始業前に資料をまとめたりメールを送ったりすることも、本来なら労働時間として扱うべき行動にあたります。それを会社側が記録していなかったり、残業代を支払っていなかった場合、法律違反に問われる可能性があります。
「早く来てくれて助かるよ」と上司に言われたとしても、タイムカードを押していなければ、その時間は労働としてカウントされません。本人はあくまで善意でやっているつもりでも、会社にとっては“見えない労働”となってしまうのです。
さらに、こうした行動が「この職場は早出が普通なんだ」という空気を作ってしまえば、結果的にブラックな働き方へとつながってしまう恐れもあります。
このあとは、こういった習慣が、周囲にどんな心理的な影響を与えるかを考えていきます。
その空気、まわりにプレッシャーかけてない?
早めに出勤して黙々と働く姿勢は、一見まじめで好印象に思われるかもしれません。ですが、その行動が知らず知らずのうちにまわりへプレッシャーを与えていることもあります。
なぜなら、人は無言の行動にも影響を受けるからです。誰かが始業前から集中して仕事をしていると、それを見た他の人が「自分も早く来ないといけないのかな」と感じたり、「あの人より遅く来た自分はやる気がないと思われそう」と不安になったりすることがあります。
例えば、毎朝30分早く来て作業している人がいる職場では、次第に他の社員も同じように早く出勤し始めることがあります。最初は気を遣っていたはずなのに、気づけばそれが“暗黙のルール”のようになり、本来の始業時間に来ていた人が浮いてしまう状況が生まれてしまいます。
このような空気が広がると、気持ちよく働ける環境が少しずつ崩れていきます。そして、次第に不満やストレスが積もっていき、人間関係のギクシャクやチームの雰囲気にも影響が出てくることがあります。
このあとお話しするのは、こうした無言のプレッシャーが、実際にトラブルへとつながってしまうケースについてです。
実はトラブルのもとになることもあるんです
職場でのちょっとした違和感が、思わぬトラブルに発展することがあります。早く出勤して仕事を始めることも、例外ではありません。
なぜなら、その行動が他の社員や上司との間に誤解や不満を生むことがあるからです。例えば「自分はこんなに頑張っているのに、誰も認めてくれない」と感じる人がいたり、「あの人だけ評価されてずるい」といった声が出てきたりすることがあります。
また、チーム内で「なぜあの人だけあんなに早く来るの?」と疑問が生まれ、それが陰口や噂につながるケースも見られます。早く来る人に悪気がなくても、まわりとのバランスが崩れることで、ちょっとした行動が人間関係のきっかけになってしまうこともあります。
実際、職場によっては「始業前の行動で評価が分かれるのは不公平」と感じた社員が上司に相談し、それがきっかけで社内ルールを見直すことになった事例もあります。
このようなリスクを減らすには、個人の頑張りだけに任せるのではなく、職場全体としてルールやマナーを整えておくことが大切です。次の見出しでは、早く出勤する人の背景にある気持ちについて考えてみましょう。
始業前に仕事する人が迷惑に思われないために

早く出勤する人の“気持ち”にも注意が必要かも
早く来て仕事を始める人の中には、「落ち着いて準備したい」「人が少ないうちに集中したい」など、それぞれに理由があることも多いものです。やる気や責任感からの行動で、決してまわりに対して何かを強制したいわけではないはずです。
とはいえ、その“前向きな気持ち”が、職場の空気や他の人の働き方とずれてしまうことがあります。特に、自分の行動がまわりにどう見られているかを意識しないまま続けていると、思いがけない誤解を生むこともあります。
たとえば、毎日ひとりで早く出勤している様子を見た同僚が、「あの人、がんばってるアピールしてるのかな」と感じてしまうようなこともあるでしょう。本人は純粋に働きやすい時間を選んでいるつもりでも、周囲の感じ方は異なることがあります。
このようなズレを防ぐには、「自分のために早く来ている」という思いと同時に、「まわりにどう影響するか」も気にかけておくことが必要です。行動の目的が同じでも、見られ方ひとつで関係性が変わってしまうことがあります。
ここからは、こうしたズレが「浮いて見える」印象につながってしまう理由を考えていきましょう。
ひとりで張り切ると浮いてしまう理由
意欲をもって仕事に取り組むことは素晴らしいことです。ただし、その張り切り具合がまわりと大きく違いすぎると、かえって孤立してしまう可能性もあります。
職場では、個人の能力や頑張りだけでなく、「まわりとの調和」も大切にされる場面が少なくありません。ひとりだけが目立つような行動を続けていると、他の社員が気を使ったり、どこか居心地の悪さを感じたりすることもあるからです。
たとえば、他の誰もいない時間に出社して、静かに作業をしている人がいると、「急がなきゃいけないのかな?」と焦ってしまう人が出てくることも。そうした雰囲気が続けば、「あの人はちょっと別の空気感だよね」と思われてしまうこともあるでしょう。
また、過剰に張り切っている様子が目につくと、「評価を狙ってるのかな?」といった誤解につながる場合もあります。努力を続けているつもりが、知らぬ間に距離を置かれてしまう原因になるのは、避けたいところです。
では、どうすればまわりとのバランスを保ちながら、良い関係を築いていけるのでしょうか。次に、そのヒントを探っていきます。
気をつけたい、まわりとのちょうどいい関係
働き方には人それぞれのペースがあります。だからこそ、誰かが極端に目立つ行動をとると、その存在がまわりに影響を与えてしまうこともあります。
「やる気があるのは良いこと」という考えは正しいですが、それが周囲の空気を乱してしまえば、本来の目的から外れてしまいます。協調性や空気を読む力も、仕事を円滑に進めるうえで欠かせない要素です。
たとえば、始業前に机に向かって資料を読み込んでいる姿を見て、「あれ?もう仕事始まってるの?」と戸惑ってしまう人がいるかもしれません。その違和感が積み重なると、「あの人とは少し距離を取りたいな」と思われてしまう可能性もあるのです。
ですので、自分が良かれと思ってやっていることでも、「まわりにどう映るか」を少しだけ意識してみることが、ちょうどいい距離感を保つためのポイントになります。
もし、「がんばっているのにうまくなじめない」「気を使いすぎてしんどい」と感じているなら、思い切って職場の環境を見直してみるのも一つの方法です。
▶︎ リクルートエージェントで無料相談してみる
自分に合った働き方を知ることで、気を張りすぎない毎日が近づいてくるかもしれません。
このあとは、こういった雰囲気のズレやトラブルを防ぐために、上司や人事がどう関わっていけるかを見ていきましょう。
上司や人事が決めておきたいルールと声かけ
早出の習慣や雰囲気によるズレを防ぐためには、個人まかせにするのではなく、上司や人事が「働き方のルール」を明確にしておくことが大切です。曖昧なままでは、人によって受け止め方が変わってしまい、行動もバラバラになりがちです。
たとえば、「始業前の時間帯は、私語や軽い準備はOKだけど業務はNG」といったガイドラインを掲示するだけでも、職場の空気は変わります。また、「早く来ている人がいても、それに合わせる必要はないよ」といった一言があると、まわりの緊張もやわらぎます。
ルールが整っていることで、早出している人も「評価のためではない」と伝えやすくなり、時間どおりに出社する人も無理せず働けるようになります。お互いに気を使いすぎず、ちょうどよい距離を保てるようになるのです。
上司や人事が「静かに仕事を始めたい人」「きっちり時間を守りたい人」どちらの気持ちも尊重しながら環境を整えることで、職場の空気がぐっとやわらかくなっていくでしょう。
「この空気、どうしても合わないな…」と感じる日が増えてきたら、少し視野を広げてみるのもひとつの方法です。
会社に行かなくても、自分のスキルを活かして働ける選択肢はいろいろあります。たとえば、在宅ワークができるクラウドソーシングサイトをのぞいてみるだけでも、気持ちが変わることがあります。
▶︎ クラウドワークスに無料登録して在宅ワークをはじめてみる
「会社だけが居場所じゃない」と気づけたとき、働き方の選択肢がぐっと広がります。
まとめ
職場にひとり、誰よりも早く来て静かに仕事を始める人。その姿は真面目で誠実に映るかもしれません。でも、毎朝それを見て「自分も早く来たほうがいいのかな…」と胸がざわついた経験はないでしょうか。
時間どおりに来ているだけなのに、なぜか遅れているように思えたり、自分のペースを保てなくなったり。そんな空気が広がると、知らないうちにストレスが積もり、人間関係にも小さなひびが入ってしまうことがあります。
しかも、始業前の労働は法律の面でもグレーゾーンになることも。
だからこそ必要なのは、誰かのがんばりに頼る職場ではなく、お互いが心地よく働けるように、ルールと気づかいを持ち寄ること。張りつめた空気より、ちょっとやさしい職場のほうが、きっとずっと長く働きやすいはずです。