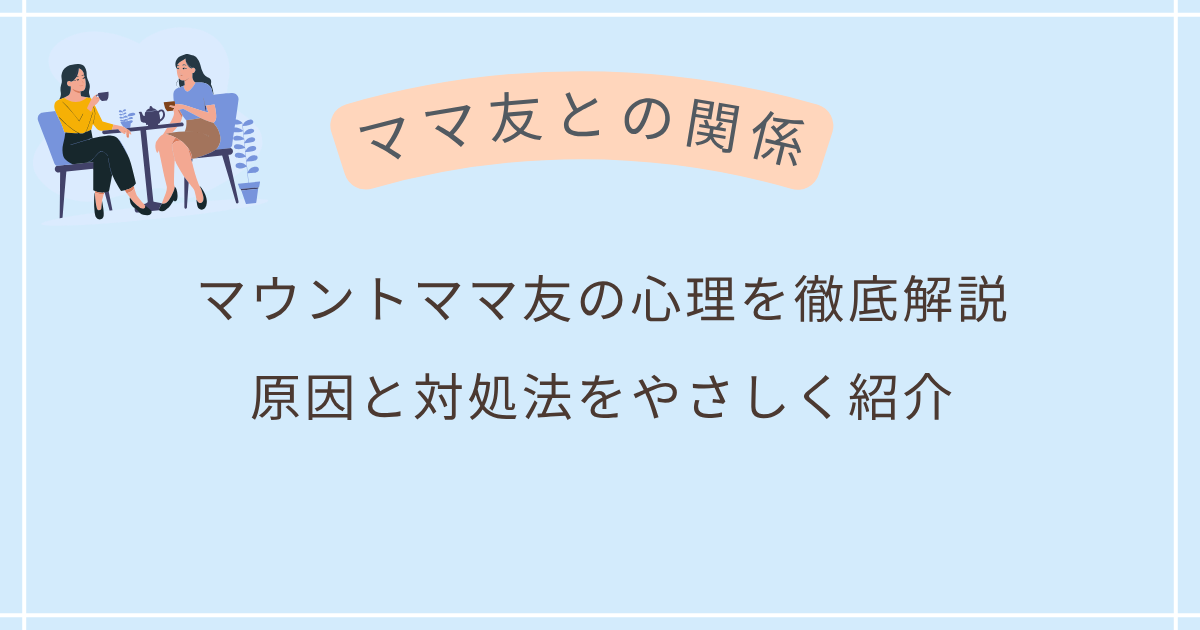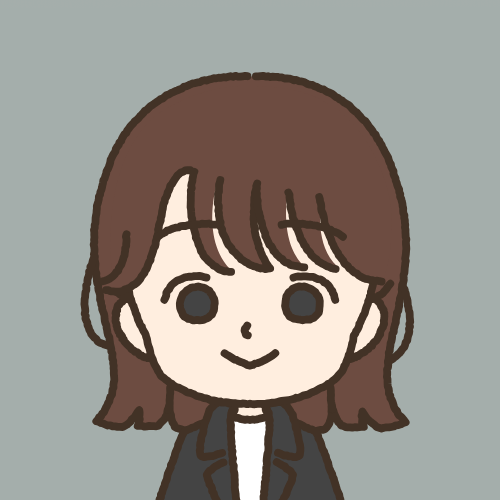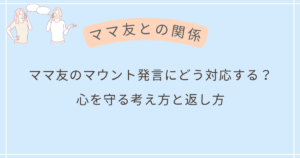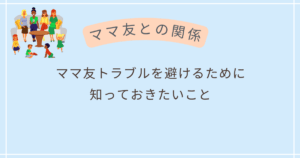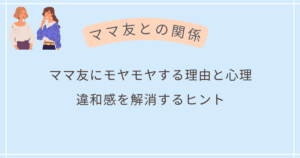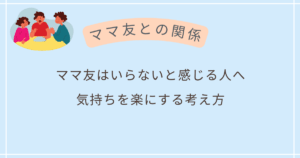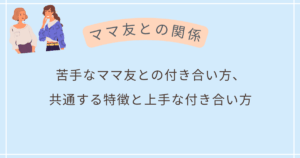ママ友との会話の中で、「なんだかいつも比べられている気がする…」と感じたことはありませんか?
もしかするとそれは、無意識のうちにマウントを取られているのかもしれません。
この記事では、ママ友がなぜマウントを取るのか、その心理や理由をわかりやすく解説します。
特徴や具体的な会話例、対処法まで丁寧に紹介していますので、モヤモヤを整理したい方はぜひ参考にしてみてください。
- ママ友がマウントを取る心理とその理由
- マウント発言の具体的な特徴や会話例
- マウントに巻き込まれない考え方と対処法
- ストレスをためない距離感の取り方
マウントママ友の心理とは?その背景を知る

ママ友マウント なぜ起こるのか?
ママ友の間でマウントが起こる背景には、不安や承認欲求が大きく関わっています。
表面上は何気ない会話でも、「うちの子は○○できるようになったの」や「うちはこの前○○に旅行したよ」など、相手より優位に立とうとする言動が見られることがあります。
これは、自分の子育てや家庭に自信が持てない人が、他者と比べることで安心しようとする心の動きです。特に、子どもの成長や家庭環境などが話題になりやすいママ友同士では、どうしても比較が生まれやすい傾向があります。
例えば、あるママが「うちはもうオムツ外れたよ」と言ったとします。一見普通の会話ですが、相手の子がまだトイレトレーニング中だと、「早くできたことを自慢された」と感じることもあるでしょう。
こうしたやり取りは、ママたちが自分の価値や育児の正しさを確かめたい気持ちから生まれているのかもしれません。そしてそれが、無意識のうちに「マウント」として現れてしまうのです。
このように、ママ友のマウントは単なる競争心というよりも、不安や孤独感が引き金になることが多いようです。では、そのようなマウントをとる人は、どのような未来を迎えるのでしょうか?次で見ていきましょう。
マウント取る人 末路はどうなる?
マウントを取り続ける人は、最終的に孤立しやすくなる傾向があります。
最初のうちは「すごいね」「頼りになるね」と周囲から反応があったとしても、繰り返されると次第に距離を置かれるようになります。
なぜなら、マウント発言を受けた側は、劣等感や疲れを感じるからです。特にママ友の世界では、相手との関係性が続きやすい分、「無理してでも付き合わないと…」という気持ちがプレッシャーにもなりかねません。
例えば、何かにつけて「うちはもっと◯◯だよ」と張り合ってくるママがいたとしましょう。最初は笑って受け流していても、会話のたびに比較されると、周囲は次第に関わりたくなくなってしまいます。
そしてもう一つは、マウントを取る側自身も満たされない状態が続くということです。他人と比較し続ける生き方は、常に不安や焦りと隣り合わせ。どれだけ周囲に勝っても、心が落ち着くことはありません。
こうした理由から、マウントを取ることは一時的な安心につながっても、長い目で見ると信頼や人間関係を失う結果になることが多いのです。
このように、マウントを取り続けることにはリスクがあります。では、もし実際にマウントを取られてしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか?次で詳しくお話しします。
マウントされたら 勝ちとは限らない理由
ママ友にマウントされたとき、「やり返したほうがいいのかな?」と思う人もいるかもしれません。
ですが、相手に勝とうとすることが、かえって自分を疲れさせてしまうことがあります。
そもそも、マウントを取ろうとする人は、「相手よりも上に立ちたい」という気持ちが強く、常に比較を前提とした会話をしてきます。
そこに真正面から対抗してしまうと、終わりのない競争に巻き込まれることになりかねません。
例えば、あるママ友が「うちは毎年海外旅行してるよ」と話してきたとします。
それに対して「うちはもっと豪華なところに行ったよ」と返したら、次はさらに相手が張り合ってくる可能性もあります。
このように、やり返せばやり返すほど、関係はどんどんストレスの多いものになってしまいます。
また、「マウントを取り返して勝った」と思っても、実際には気持ちがすっきりしないこともあるでしょう。
なぜなら、相手に勝ったところで、根本的に自分の価値が上がるわけではないからです。
このように考えると、マウントに勝とうとすること自体が、あまり意味のあることではないのかもしれません。
むしろ、自分がどう感じるか、どう関わるかを意識することのほうが、よほど気持ちがラクになります。
では、具体的にどうやってママ友のマウントに対処していけばよいのでしょうか?次ではそのコツを紹介していきます。
マウントママ友の心理の見分け方と関わり方

さりげなくマウンティングしてくるママ友の特徴とは
マウンティングをするママ友の中には、あからさまではなく、さりげなく優位性をアピールしてくるタイプもいます。
一見感じがよくて親しみやすそうに見えても、話の中に「ん?」と違和感を覚えることがあれば、無意識のマウントが隠れているかもしれません。
特徴のひとつとして、「褒めながら比べる」言い方があります。
例えば、「○○ちゃんも頑張ってるね。でもうちはもうひとりで何でもできるよ」といった感じです。
やわらかい口調であっても、自分の子や家庭の方が上だと印象づけるような言い回しが目立ちます。
他にも、「アドバイスのように見せかけた指摘」も特徴的です。たとえば「そのやり方もいいけど、うちはこうしてるよ。
こっちの方が楽だよ」など、自分のやり方を正解として押しつけるような表現を使うことがあります。
また、会話の中で自然と高価な物や教育熱心さをアピールしてくる人もいます。
本人はただの雑談のつもりでも、聞いている側がプレッシャーを感じる内容であれば、それもさりげないマウンティングかもしれません。
こうした特徴に気づけると、相手の言動に振り回されにくくなります。
では、実際の会話ではどんなやり取りがマウントになっているのでしょうか?次で具体的な例を見ていきます。
マウントをとる 会話 例 ママ友とのやりとり
ママ友との会話の中で、気づかないうちにマウントを取られている場面は意外と多いものです。
ここでは、よくあるやりとりの具体例を挙げながら、どこにマウントの要素があるのかを見ていきましょう。
たとえばこんな会話があります。
例1:教育関連の会話

最近、うちの子もようやくひらがなを覚えてきたんだ



え〜すごいね!でもうちは2歳のころから読み書きできてたよ
→この会話では、一度は褒めているように見えますが、そのあとに「うちの方が上」と言いたい気持ちが表れています。
例2:家計や生活レベルの話



うちは近所のスーパーで安くまとめ買いしてるよ



そうなんだ〜。うちは有機野菜を取り寄せてて、ちょっと高いけど安心なのよ
→相手のやり方を否定せずに、自分の生活レベルをさりげなく上に見せているパターンです。
例3:夫や家庭についての話



最近、夫がちょっと家事を手伝ってくれて助かってるんだ



いいね!でもうちは家事も育児も全部夫がやってくれるから本当に楽
→「あなたも頑張ってるけど、うちはもっといいよ」と遠回しに言っている印象を受けやすい会話です。
このように、会話の内容に「比べてどうこう」や「うちはもっと」というフレーズが入ると、聞いている側は無意識に劣等感を抱きやすくなります。
では、そうしたマウント発言に対して、どうやって対応すればよいのでしょうか?次は、その具体的な対処法についてお話しします。
ママ友との距離感の取り方
ママ友との関係は、近すぎても遠すぎてもストレスになりやすいものです。
心地よい距離を保つことで、お互いに無理せず自然な付き合い方ができるようになります。
まず意識したいのは、「全部の人と仲良くする必要はない」ということです。
ママ友は、子どもを通しての関係であり、必ずしも深い付き合いを求められるわけではありません。
相手と合わないと感じたときは、無理に話を合わせるよりも、少し距離を取るほうが気持ちがラクになります。
例えば、公園で会うときだけの軽いあいさつや、その場限りの雑談で済ませるのもひとつの方法です。
LINEなどでのやり取りも、返信を急がず「今は忙しいから、また今度」と気持ちを切り替えるだけで、だいぶストレスが減ることがあります。
そしてもうひとつ大切なのは、自分の中で「ここまではOK」「これは踏み込まれたくない」というラインをはっきりさせておくことです。
それを自覚しておけば、相手のペースに飲み込まれずに、自分らしい関係を築けるようになります。
このように、ママ友との距離感は自分でコントロールしてよいものです。
近づきすぎない付き合い方ができれば、マウントされる場面も自然と減っていきます。
では、もしマウントされるような場面に遭遇したとき、どのように考え方を切り替えていけばよいのでしょうか?次でそのヒントをお伝えします。


マウントをとるママ友の心理、対処と心の整理


マウントをとるママ友 対処のコツと心構え
マウントを取ってくるママ友に出会ったとき、真正面から受け止めすぎないことが、まずひとつのコツになります。言い返したり、対抗しようとすると、気持ちが余計に乱れてしまうことも少なくありません。
対処の基本は、「聞き流す」「深く関わらない」「無理に張り合わない」の3つです。
マウント発言に対しては、「そうなんだね」「へぇ、すごいね」と軽く受け流すことで、相手のペースに巻き込まれずに済みます。
例えば、「うちはもうピアノ始めたよ、週3で通ってるの」と言われた場合、そこで「うちも何か習わせた方がいいかな…」と焦るのではなく、「子どもが楽しめてるなら何よりだね」と答えるだけでも、十分な返しになります。
そして、心構えとして意識したいのは、「相手は相手、自分は自分」と切り分けて考えることです。
相手がどれだけ自慢話をしてきても、それがあなたやお子さんの価値に影響することはありません。
こうしたスタンスを保てれば、必要以上に悩むことも減ります。
ちょっとモヤモヤがたまった日は、自分を癒す時間をつくってみませんか?
アロマや入浴剤、快眠グッズなど、気分転換にぴったりのアイテムをそろえておくと、気持ちの切り替えがラクになります。
👉 リラックスアイテムをチェック!
次は、さらに気持ちを軽くするために「気にしない」という考え方に焦点を当ててみましょう。
ママ友のマウント 気にしない方法とは
ママ友のマウントに悩まされがちな人は、「気にしない」という姿勢を少しずつでも身につけていくことが気持ちを軽くする近道です。
完璧にスルーできなくても、「あまり深く考えない」で済ませるクセをつけるだけで、心の負担がかなり違ってきます。
まず意識したいのは、「その人の価値観=自分の価値観ではない」と気づくことです。
どれだけ相手が家庭のことや子どものことを語ってきても、それはその人の世界での話。すべてを真に受けて自分と比べる必要はありません。
例えば、周りのママが「もう○○できるようになったの?早いね」と言ってきたとしても、あなたの子どものペースはあなたの子のものです。
他人の評価ではなく、自分が子どもと向き合ってどう感じているかの方がよほど大切だといえます。
また、情報や話をそのまま受け取らず、「そういう考え方もあるんだな」と客観的に捉える練習をすると、マウントされても深く刺さりにくくなります。
こうして、自分の心に余裕を持てるようになれば、マウントを取られても揺らがずにいられるようになります。
では、マウンティングの空気に飲まれないためには、どんな考え方が役立つのでしょうか?次で詳しく見ていきます。
マウンティングに巻き込まれない考え方
マウンティングをしてくるママ友がいると、気づかないうちに気持ちがざわついたり、イライラしたりすることがあります。
でも、相手の言動に振り回されないためには、考え方のクセを少し変えることが効果的です。
まずは、「マウント=自分への攻撃」と決めつけすぎないことです。
もちろん悪意を感じる発言もありますが、すべてのマウントが相手の意図的な行動とは限りません。中には、ただの自慢話や日常の報告として話しているだけ、という場合もあります。
例えば、「うちは毎日手作りの夕食なの」と言われたとき、それを「私の手抜きを責めてる?」と受け取ってしまうと、心がすぐに反応してしまいます。
でも、「へぇ、そういうのが好きな人なんだな」と一歩引いて聞くと、感情が乱れにくくなります。
また、マウントされる=負けではありません。
相手にどう思われたとしても、あなた自身が自分の生活や子育てに納得していれば、それで充分です。
こうした考え方を持っていると、周囲のマウンティングにも巻き込まれにくくなります。では、実際の関わりの中でストレスをためずに付き合うには、どんな工夫ができるでしょうか?次で詳しく見ていきます。
ストレスをためない関わり方とは
ママ友との関係でストレスをためないためには、自分の心と時間を守る意識を持つことがポイントです。
すべてに気を遣っていると疲れてしまいますし、相手に合わせすぎると、自分のペースが崩れてしまうこともあります。
たとえば、無理に話を合わせようとせず、「今日は聞き役にまわろう」と決めて距離を取るのも一つの方法です。
相手の話を受け流すスタンスを取ることで、心の余裕が生まれます。
さらに、グループの中で苦手な人がいる場合は、物理的な距離も意識してみてください。
集まりに毎回参加する必要はありませんし、LINEの返信もすぐに返す義務はありません。自分のペースを大事にしていいのです。
また、自分の中に「こうでなきゃ」という理想像があると、他人との違いがストレスになります。
「私は私」と思えるようになると、相手の態度に一喜一憂することが減っていきます。
このように、自分の軸を持って関わることで、ママ友とのやり取りもずっとラクになります。では、そもそも無理に仲良くする必要があるのかどうかについても、最後に触れておきましょう。
無理に仲良くしない選択肢もあり
ママ友との関係で悩んでしまう人の多くが、「仲良くしなければいけない」という思い込みにとらわれてしまいがちです。でも、すべての人と深く関わる必要はありません。距離を取るという選択も、自分や家族を守るひとつの手段です。
実際には、「会えばあいさつするけれど、それ以上は踏み込まない」程度の関係がちょうどいいと感じる人も多くいます。軽い雑談や一時的なやり取りだけで済む関係性は、精神的な負担も少なくて済みます。
また、ランチの誘いやLINEグループの会話にプレッシャーを感じているなら、参加を断ったり既読スルーすることも悪いことではありません。あなたの生活や気持ちを優先していいのです。
ママ友との関係にモヤモヤしてしまうと、「自分のせいかも…」と必要以上に責めてしまうこともありますよね。でも、誰とどう付き合うかは本来自分で選べること。心の距離を置くのは逃げではなく、自分を大切にする行動です。
関係を断ち切るには少し勇気がいりますが、そんなときにそっと背中を押してくれる本があると安心できます。
→ 人間関係に疲れたときに読みたい一冊はこちら
ここまで読んでいただいた方は、マウントするママ友の心理や関わり方に少しずつヒントを見つけられたのではないでしょうか。
次は、記事のまとめとして、押さえておきたいポイントを整理してみましょう。
まとめ
ママ友との関係でマウントに悩む人は少なくありません。その背景には、不安や承認欲求が関係していることが多いようです。
自分に自信がない分、子育てや家庭の話題で優位に立とうとするのです。会話の中では、褒めながら比べる発言や、アドバイス風の自慢が見られることもあります。
こうしたマウントには張り合わず、聞き流す姿勢が効果的です。無理に仲良くする必要はなく、適度な距離感を保つことで心がラクになります。
気にしすぎず、自分のペースを大切にしましょう。