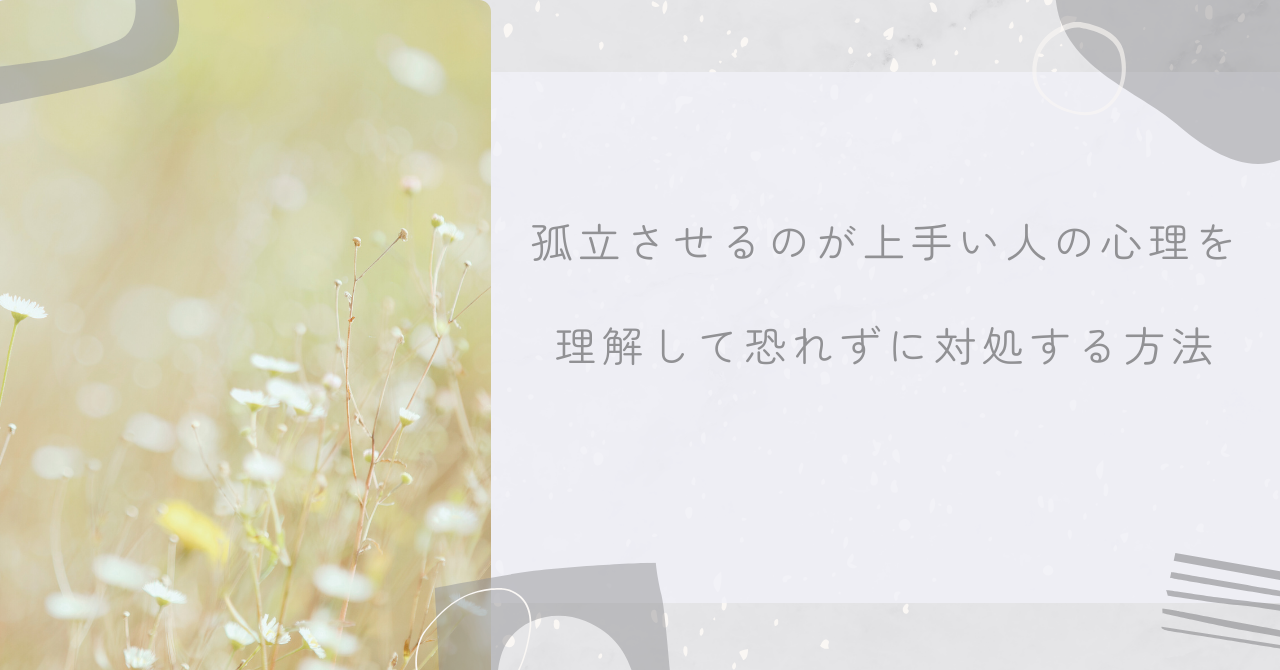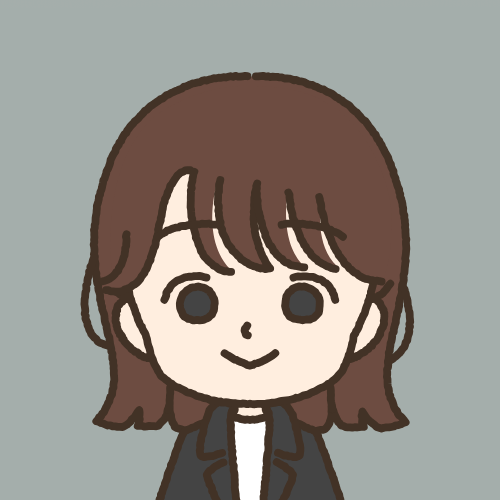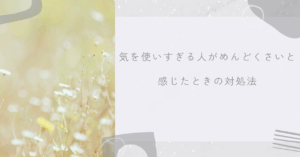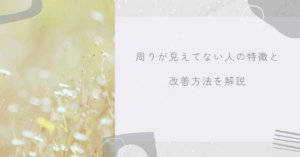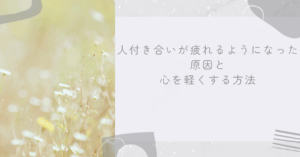職場や人間関係の中で、なぜか一部の人が孤立させられてしまうことがあります。
背景には、孤立させるのが上手い人の存在が関わっている場合があります。彼らの心理を理解しないままでは、ただ怖いと感じるだけで不安が増してしまいがちです。しかし、その心理を読み解き、効果的な対処法を知ることで、恐怖を和らげ冷静に向き合うことができます。
本記事では、孤立を仕掛ける人の特徴や行動の裏にある心理、そして安心して関わるための方法を分かりやすく解説します。
- 孤立させるのが上手い人の心理が理解できる
- 職場で孤立が起こる原因と背景を知れる
- ターゲットにされやすい人の特徴を理解できる
- 孤立させられたときの安心できる対処法が学べる
孤立させるのが上手い人の心理

孤立させる人の末路とは
孤立させる人は、短い期間であれば周囲を思い通りに動かし、強い立場に立つことができます。
しかし、そうしたやり方は長続きしません。人間関係を無理にコントロールしようとする行動は、いずれ周囲から見抜かれてしまい、徐々に信頼を失っていきます。その結果、孤立させていた本人が最後には孤立してしまうという状況に陥ることも少なくありません。
厚生労働省が公表している労働相談のデータでも、いじめや嫌がらせの相談件数は年々増えています(出典:厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」)。
このような行動を繰り返す人は組織内で注目を浴びやすく、次第に周囲が距離を置くようになるのです。
仕事の場面では、協力や信頼が欠かせません。孤立させる行動を続ける人は、チームでの協力を得られず、昇進やキャリアアップのチャンスを逃すことがあります。
つまり、孤立させる人の末路は決して明るいものではなく、むしろ自分自身を追い込んでしまうものだと言えるでしょう。
孤立させられる職場で起きること
職場で誰かが孤立すると、最初に影響が出るのはチームの雰囲気です。
孤立させられた人は萎縮して意見を言いづらくなり、その場にいる全員の発言も減ってしまいます。結果として、会議が停滞しやすくなり、業務のスピードや質に悪影響が出ることがあります。
このような状況が続くと、周りの人も「自分も同じように孤立させられるのでは」と感じ、安心して意見を言えなくなります。Googleの研究で「心理的安全性」が高いチームほど成果を出していることが明らかになっていますが、孤立が広がる職場ではその逆の現象が起きてしまうのです。
さらに、孤立によるストレスはターゲットになった人の心身に影響し、離職や人材流出にもつながります。厚生労働省の調査でも、職場でのいじめや孤立はメンタル不調の大きな原因の一つとされています(出典:厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する調査」)。
つまり、孤立は個人の問題にとどまらず、組織全体の健全性を損なう大きなリスクなのです。
職場で孤立のターゲットになる人
孤立のターゲットにされやすい人には、いくつかの特徴があります。
たとえば、周囲とは違う意見を持ちやすい人は、新しい発想を持っていても浮いて見られることがあり、孤立のきっかけになってしまうことがあります。
また、実力が高く目立つ人もターゲットにされやすい傾向があります。周囲から評価や注目を集める人は、孤立させる側にとって脅威となるからです。反対に、控えめであまり自己主張をしない人も、攻撃しやすい相手として狙われやすくなります。
ただし、これらの特徴は必ずしも弱点ではありません。むしろ「個性」や「強み」である場合が多いのです。心理学には「スケープゴート理論」という考え方があり、集団の不安や不満が一人に集中してしまうことがあります。
つまり、孤立はターゲットの性格や能力の問題ではなく、人間関係の力学によって生じる現象だと理解しておくことが大切です。
劣等感が孤立を生む理由
孤立させる人の心の奥には、強い劣等感や承認欲求が隠れていることが多いと考えられます。
自分よりも優れた人がいると不安になり、その不安を和らげるために相手を排除しようとするのです。孤立させることで自分の立場を守り、周囲の注目を独占しようとする心理が働いています。
一見すると強い態度に見えても、実際には心の弱さや自信のなさが行動の背景にあります。
心理学では「優越の錯覚」と呼ばれる現象があり、自分が他者よりも優れていると感じたいがために周囲を下に見る傾向が指摘されています。
この傾向が強い人は、自分を優位に見せるために孤立を仕掛けることがあります。
劣等感そのものは誰にでもありますが、それを人間関係に持ち込み、他者を排除する形で解消しようとする点に問題があります。
このことを理解すると、孤立させる人の行動は「怖い存在」ではなく「不安を抱えた人の振る舞い」と見えてきます。必要以上に恐れるのではなく、冷静に距離を保ちながら向き合うことが大切です。
孤立させるのが上手い人への対処法

孤立させる人に欠けているもの
孤立を仕掛ける人には、共感力が不足していることがよく見られます。
他人の立場に立って考えることができず、相手の気持ちに無頓着なため、人を傷つけている自覚がないまま行動してしまうのです。
また、人間関係を協力や信頼で築くよりも、力関係や支配で成り立たせようとする傾向もあります。これは短期的にはうまくいくように見えても、長期的には信頼関係を失い、周囲からのサポートを得られなくなる原因となります。
共感力や協調性が欠けていると、孤立させる人自身が困難に直面したときに助けてもらえなくなります。
本人にとっても不利益であることを理解すると、孤立させる行動が持続可能でないことが見えてきます。相手に過度な期待をせず、一定の距離を取りながら関わる姿勢が安心につながります。
孤立させられるときの心の守り方
もし自分が孤立させられていると感じたら、まず大切なのは「自分を責めすぎないこと」です。
孤立の原因は必ずしも本人の性格や能力にあるわけではなく、多くの場合は相手の心理や人間関係の力学が背景にあるからです。
心を守るためには、自分の考えや行動を肯定する習慣を持つことが役立ちます。例えば、日々の小さな成果や良かった出来事を記録することで、自信を保ちやすくなります。
また、信頼できる同僚や友人に気持ちを打ち明けることも、孤立感を和らげる効果があります。
心理学的には「ソーシャルサポート」と呼ばれる周囲からの支えが、ストレスの軽減に大きな役割を果たすとされています。
孤立の経験を内に抱え込まず、外に出すことで不安や恐怖は次第に軽くなります。心の守り方を身につけることが、孤立に巻き込まれても自分らしく過ごすための基盤となります。
日頃の信頼関係で孤立を防ぐ方法
孤立を避けるためには、日常の小さなやり取りから信頼関係を育てることが役立ちます。
たとえば、毎日の挨拶やちょっとした感謝の言葉は、相手との距離を縮める大切なきっかけになります。こうした積み重ねは目立たないようでいて、人間関係の土台をしっかりと作ってくれます。
また、特定の人だけでなく、複数の人とつながりを持つことも安心につながります。
人間関係の幅を広げておくことで、もし一時的に一部の人との関係がぎくしゃくしても、孤立に追い込まれるリスクを減らせるからです。これは心理学でいう「ネットワークの多様性」がストレス対処に有効であることと通じています。
さらに、信頼を築く際に大切なのは「双方向性」です。一方的に助けを求めるだけでなく、自分も相手を支える姿勢を持つことで関係は安定します。互いに支え合える環境を整えることが、孤立を防ぐ最も確かな方法といえるでしょう。
記録を残して安心する方法
孤立させられていると感じたときは、感情的に受け止めるだけでなく、具体的な記録を残すことが冷静さを保つ助けになります。
日付、場所、発言内容、そのときの状況などを簡潔に書き留めておくと、客観的に出来事を振り返ることができます。
こうした記録は、もし上司や人事部に相談するときの根拠にもなります。また、法的な手続きを検討する場面でも有効な証拠となり得ます。厚生労働省でも、職場でのいじめや嫌がらせへの対応において、事実の記録を残すことの重要性を指摘しています。
記録を残すことは単に証拠を集めるだけでなく、「自分は状況をコントロールできている」という感覚を持つための手段でもあります。
孤立に直面すると不安でいっぱいになりがちですが、冷静に状況を書き出すことで安心感が得られ、心の負担を軽くすることができるのです。
まとめ
孤立させる人は一時的に優位に立てても、いずれ信頼を失い、自ら孤立する可能性があります。職場での孤立は個人だけでなく組織全体にも悪影響を及ぼします。
ターゲットにされやすいのは、優秀さや控えめな性格を持つ人であり、その背景には孤立させる側の劣等感や承認欲求が隠れています。孤立を仕掛ける人には共感力が欠けているため、過度に恐れず冷静に距離を取ることが大切です。
孤立させられたときは自分を責めず、信頼できる人に気持ちを話し、日々の信頼関係を積み重ねることでリスクを減らせます。記録を残すことも安心につながり、心理的な負担を和らげます。
孤立させる人の心理を理解すれば、不安に振り回されず落ち着いて向き合えるようになります。自分を守りながら信頼を育てることで、安心して前に進むことができるのです。