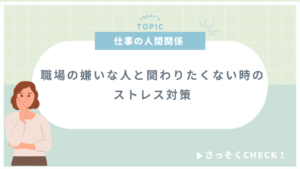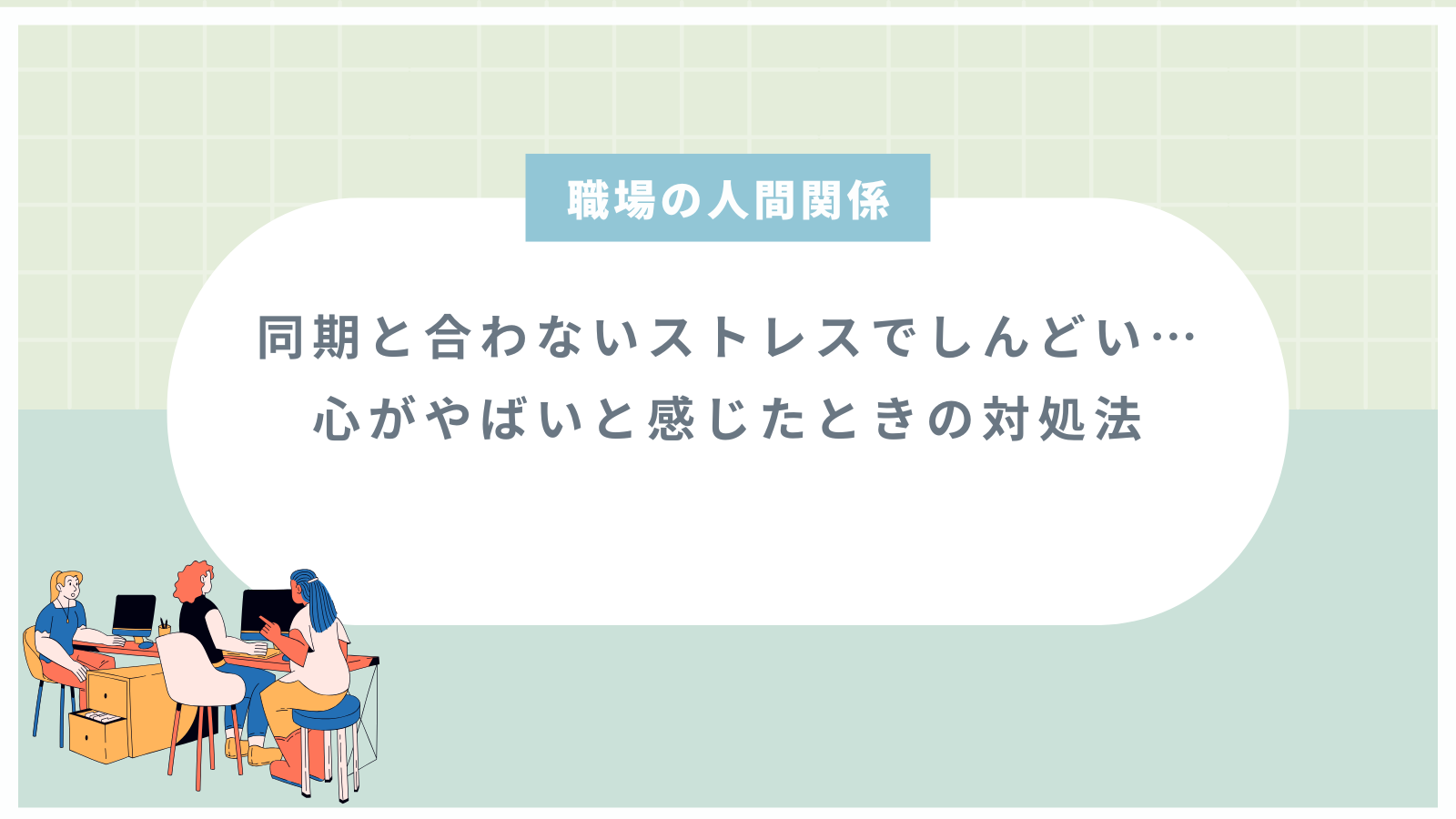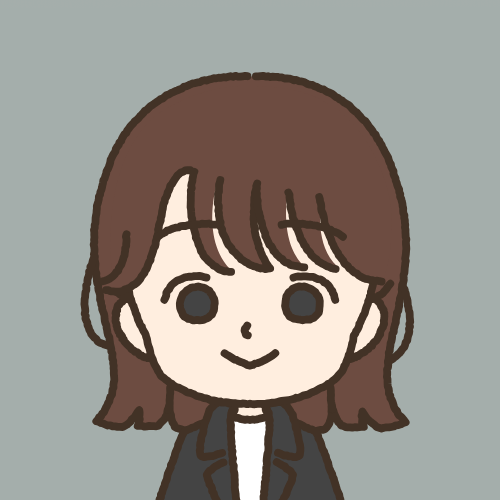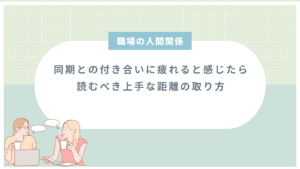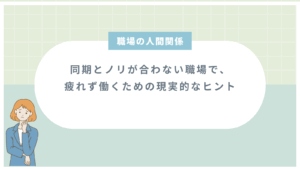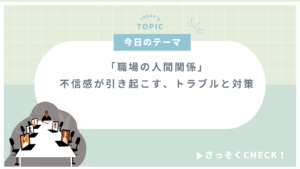職場の同期とうまくいかず、ストレスを抱えている方は少なくありません。
「もう限界かもしれない」「辞めたい」と感じるほど悩んでいるなら、それは決しておかしなことではなく、心がサインを出している状態です。
同期とは同じ時期に入社したというだけで、性格や価値観が合うとは限りません。むしろ、無理に仲良くしようとすることで疲れてしまったり、比較される環境に苦しんだりすることもあります。
このページでは、同期と合わないことで生まれるストレスの正体や、少しずつ心を楽にする方法、そして「辞めたい」と思ったときの考え方などを、やさしい視点でまとめています。
ひとつひとつの項目が、あなたの心にそっと寄り添えたらうれしいです。
- 同期と合わない原因やストレスの正体がわかる
- 無理せず距離を取る具体的な方法がわかる
- 辞めたいと感じたときの整理の仕方がわかる
- 転職を考える際の準備や考え方がわかる
同期と合わないストレスは誰にでも起こりうる悩みです

なぜ同期にストレスを感じるのか?
同期との関係にモヤモヤを抱える人は少なくありません。
とくに「一緒に入社した」というだけで、価値観や仕事の進め方が違う相手と、無理に付き合うことがストレスの原因になりがちです。
その理由は、「同じ立場=仲良くしなければならない」という無言のプレッシャーにあります。周囲が自然に打ち解けているように見えると、自分だけがうまくやれていない気がしてしまうこともあるでしょう。
例えば、同期が集まってランチに行く流れができていたとします。断ることで「ノリが悪い」「冷たい」と思われたくない一方で、無理して参加すると心が疲れてしまう。こうした場面の繰り返しが積もって、ストレスとなっていきます。
さらに、同期との間に比較が生まれやすい点も見逃せません。評価や昇進、上司との関係など、目に見えない競争意識があると、相手の一挙手一投足に敏感になり、安心して過ごせなくなります。
こうした状態が続くと、「気にしすぎかな」と自分を責めてしまうことも。けれど、合わない人がいて当然という視点に立つと、気持ちが少し楽になります。
次は、そもそもどんな人が「同期付き合いが疲れる」と感じやすいのかを見ていきましょう。
「同期付き合い疲れる」と感じる人の特徴
同期との関係が「しんどい」「めんどう」と感じやすい人には、いくつか共通する傾向があります。
主に、人との距離感を大切にするタイプの人は、特に疲れを感じやすいようです。自分の時間やペースを尊重したい人にとって、頻繁な同期飲み会やグループLINEのやりとりは、義務感が強くなりがちです。
たとえば、「断るのが苦手」「空気を読んで合わせてしまう」といった性格の人は、本音では参加したくない場面でも無理をしてしまいます。その結果、心のエネルギーがすり減ってしまうのです。
また、「職場とプライベートをしっかり分けたい」という考えを持っている人も、職場の人間関係に深く入り込むことにストレスを感じやすくなります。こうしたタイプは、必要以上に関わることが「自分らしさを失う」ことにつながると感じることもあります。
一方で、気配りができる反面、「嫌われたくない」という思いが強い人も要注意です。相手の期待に応えようと頑張りすぎることで、自分を押し殺してしまう傾向があります。
次は、こうした気疲れやストレスにどう向き合い、距離を取っていくかについて具体的に解説していきます。
同期2人しかいないと余計に合わないと感じる理由
同期がたくさんいれば、苦手な人を自然に避けることもできます。
しかし、同期が2人しかいない場合、その関係性は一対一になりやすく、どうしても気を遣う場面が増えてしまいます。
その理由として、「逃げ場がない」という状況が大きく影響しています。気が合わなくても、他の人との関わりで中和されることがなく、常に相手と向き合わなければならない状態が続くため、ちょっとした違和感も強く感じやすくなるのです。
たとえば、相手が無口だったり、逆に自分ばかり話したがるタイプだったとします。会話のリズムが合わないと、雑談ひとつでもストレスになってしまうことがあります。また、「協力すべき関係」とされやすい場面が多く、一緒に行動することが前提のような雰囲気も、プレッシャーのもとになります。
さらに、周囲の人から「仲が良いはず」という目で見られることも、心の負担につながります。本当は無理しているのに、表面上は仲良くしているふりをする必要があると、どんどん心の余裕がなくなっていきます。
このように、人数が少ない環境だからこそ、人間関係のバランスが取りにくくなり、合わない相手へのストレスが増幅されやすくなるのです。
次は、そんな相手がもし「やばいかも?」と思ったとき、どんな点に注意すべきかを見ていきましょう。
同期がやばいやつだと気づいたときのサイン
何気ないやり取りの中で、「この人ちょっとおかしいかも…」と感じたことはありませんか?
一見普通に見える同期でも、距離を置いた方がいいタイプは確かに存在します。
よくあるサインのひとつは、平気で他人の悪口を言うことです。まだ関係が浅いうちから誰かの悪評を口にする人は、信用できない可能性が高いです。自分のいないところでは、あなたのことも同じように言っているかもしれません。
また、他人のミスを過剰に責めたり、自分の失敗をすぐ他人のせいにするのも特徴です。責任を取る意識がない人と組むと、トラブルが起きたときに巻き込まれやすくなります。
さらに、嘘をつく頻度が高い人にも要注意です。話がいつも食い違ったり、小さなことでもつじつまが合わない場合は、少し距離を取るほうが安全です。
こうしたサインに気づいたら、「深く関わらない」「必要な会話だけにとどめる」といった行動が自分を守る助けになります。
次は、こうしたタイプの同期とうまく距離をとりながら、心のバランスを保つ方法についてお伝えしていきます。
同期と合わないストレスを減らす方法と向き合い方

同期にやる気がないとき、どう接すればいい?
同期がやる気を出していない様子を見て、戸惑った経験はないでしょうか。
自分は頑張っているのに、相手が手を抜いていたり、文句ばかり言っていたりすると、不公平に感じたり、モチベーションが下がってしまうこともあります。
このようなときに心がけたいのは、「相手を変えようとしない」ことです。人にはそれぞれのペースや価値観があり、今は単に疲れていたり、合わない環境で力を出せていないだけかもしれません。
例えば、同期が明らかにやる気を出していない場面に直面した場合でも、「自分の仕事に集中する」「一線を引く」といった対応を意識すると、無用なストレスを避けることができます。直接注意したくなる気持ちもあるかもしれませんが、関係が悪化するリスクも考慮する必要があります。
また、業務に支障が出るほどであれば、信頼できる上司や先輩に相談することもひとつの方法です。自分一人で抱え込むより、客観的な意見を得ることで気持ちが整理されることもあります。
次に紹介するのは、やる気のない同期だけでなく、「そもそも合わない」と感じる相手との距離の取り方についてです。
合わない同期と距離を取る具体的な方法
「この人とはどうしても合わない」と感じたとき、その関係にどう向き合えばいいか悩む人は多いものです。
気まずくなりたくない一方で、無理して付き合い続けると、心がどんどん疲れていってしまいます。
そこでまず意識したいのは、「適度な距離感を持って関わる」という姿勢です。完全に避けるのではなく、業務上必要な部分だけにとどめることがポイントになります。
例えば、雑談を無理に続けるのではなく、必要なことだけを端的に伝えるようにしたり、ランチや飲み会の誘いには「予定があって」とやんわり断ることで、自然な距離を保てます。また、グループLINEなども、自分に関係のある話題だけに返信するなどの線引きをすると、消耗を減らすことができます。
もうひとつ効果的なのは、「自分の時間を充実させること」です。プライベートで趣味やリラックスできる時間を持つことで、職場での人間関係に振り回されにくくなります。
職場の人間関係に疲れたときは、ひとりで抱え込まずに話せる場所を持つことも大切です。
【エキサイトお悩み相談室】なら、匿名でカウンセラーに相談できるので安心です。
初めての方は割引制度もあるので、気軽に試しやすいのも魅力です。
▶エキサイトお悩み相談室はコチラ
次は、そうしたストレスから「辞めたい」と感じてしまったときの考え方や行動のヒントについて解説していきます。
同期と合わないから辞めたいと思ったら読むべきこと
同期とうまくいかず、「もう辞めたい」と思うことは珍しくありません。
一緒に働く相手がストレスの原因になっていると、毎日がつらくなってしまうのも無理はないでしょう。
ただ、辞めたいと思ったときこそ、一度立ち止まって「何に一番つらさを感じているのか」を整理してみることが大切です。たとえば、「合わないから辞めたい」の中にも、具体的には「毎日の会話が気まずい」「一緒に仕事するのが苦痛」といった要素が含まれているかもしれません。
私の場合で言えば、気まずい関係に耐え続けるよりも、誰かに相談することで状況が変わった経験があります。信頼できる先輩や上司に話すことで、自分だけが悩んでいたわけではないと気づけたり、別の仕事を任されたりして気が楽になったケースもあります。
もちろん、どうしても関係が改善せず、自分らしく働けないと感じた場合は、環境を変える選択も考えられます。ただし、その判断を急ぐ前に、「本当に職場全体が合わないのか」それとも「同期だけがつらいのか」を見極めることが大切です。
ここからは、実際に「転職」という選択肢についても考えてみましょう。
同期と合わないことで転職を考えるのはアリ?
同期とうまくいかないことがきっかけで、転職を意識するようになった人もいるかもしれません。
このとき、「たかが同期との関係で転職なんて…」と自分を責めてしまう人もいますが、それは決しておかしなことではありません。
実際、職場の人間関係は、働き続けるうえで大きな影響を与えます。毎日顔を合わせる相手との関係がストレスになっていると、集中力や意欲が低下し、他の仕事にも支障が出てしまうことがあります。
例えば、仕事の進め方や価値観があまりに違っている場合、些細なやり取りでもギスギスしてしまい、日々の業務が負担になります。そうなると、いくら仕事内容が好きでも、長く働くのは難しくなってしまうものです。
ただし、転職を考える際は、「どんな職場なら自分は気持ちよく働けそうか」を明確にすることが欠かせません。勢いだけで次の会社を選んでしまうと、また似たような悩みに直面する可能性があります。
このように考えると、「同期と合わないから転職を検討すること」自体はおかしくありませんが、判断する前に一度、理想の働き方を整理してみることが大切になります。
次は、そんなときに役立つ準備や行動のステップについて紹介していきます。
辞めたい・転職したいと感じたらやるべき準備
「もう無理かも」「今の職場から離れたい」と思うようになったとき、感情のままに動くのではなく、まずは冷静に準備を始めることが大切です。
思いつきで退職してしまうと、次の仕事が決まらず後悔する可能性もあるからです。
まず最初にやるべきことは、「なぜ辞めたいのか」を整理することです。人間関係なのか、仕事内容なのか、それとも職場の雰囲気なのか。理由があいまいなまま転職しても、同じような問題にぶつかるかもしれません。
次に、自分のスキルや経験を見直してみましょう。例えば、今の仕事で身につけたことを箇条書きにしてみると、自分の強みや次に活かせるポイントが見えてきます。それをもとに、どんな仕事が合っているのか、どんな働き方をしたいのかを考えると方向性が見えやすくなります。
それから、求人サイトや転職エージェントに登録して情報収集を始めるのもひとつの方法です。すぐに応募しなくても、今の自分の市場価値を知ることで、気持ちの整理や将来の選択に役立ちます。
また、退職までのスケジュールや、次の職場が決まるまでの生活費などもシミュレーションしておくと、いざというときにも焦らずに動けます。
このように、辞めたい気持ちが出てきたときは「すぐ辞める」よりも「準備を始める」ことが、あとで自分を助けてくれることにつながります。
ただ、転職を考える際は、「どんな職場なら自分は気持ちよく働けそうか」を明確にすることが欠かせません。
今すぐ転職を決める必要はなくても、転職エージェントに相談して“今の自分に合う職場ってどんなところだろう?”を一緒に整理してもらうのも一つの方法です。
たとえば、リクルートエージェントでは、職場環境の悩みも含めて話を聞いてもらえます。まずは無料相談から試してみてもよいかもしれません。
\ 今の職場に限界を感じたら /
まとめ
同期との関係にモヤモヤを感じること、ありますよね。
「一緒に入社しただけで仲良くしなきゃいけないの?」と疑問に思うこともあるかもしれません。
周りと比べてしまったり、無理に付き合おうとして疲れてしまうこともあると思います。
とくに、人との距離感を大事にしたいタイプの方にとっては、頻繁なやり取りや集まりがしんどく感じることもあるのではないでしょうか。
もし、やる気のなさが目立ったり、陰口が多いなど気になる点がある同期なら、無理せず少し距離を置くこともひとつの選択です。
「辞めたいな」と感じるようになったら、焦らず気持ちを整理して、これからのことをゆっくり考えてみてもいいと思います。
自分のペースで、心が少し楽になる方向に進んでいけたら安心ですね。